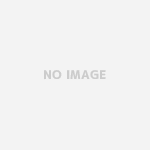対象とすると、スピーカのコーンの動きを制御対象にするか(モーションフィードバック)、その前のアンプの出力を制御対象にするかは、さておき、
まずそもそも、
①入力信号の出力電圧レベルと、帰還信号のレベルを合わせないといけないし、
(それにより、初めて制御といえるものになる。)
②それだけではなまくらで、応答が非常に遅い制御系となるので、
速度フィードバックなどを加える。
それにより初めて、まともにネガティブフィードバックが機能し始める。
だから、「化粧程度に6dbネガティブフィードバックをかけました」という記事を見ると、違和感を感じる。
「耳派」を歌うライターの先生方からすると、いくら試行錯誤して部品定数を変えても、
そういう理論がなしにして、ネガティブフィードバックがよくないという結論以外にたどりつけないだろうし、ネガティブフィードバックのアンプがもっさりしていて当たり前ではないか、思えてくる。
上記の通り、ネガティブフィードバックを理論的に、解析した記事は少なく、
電源を合わせて、球を変えて、作ってみましたという記事が多いが、
ラジオ技術の、氏家高明先生、D-NFBの野呂真一先生と、石塚俊先生の記事は、非常に精神性あふれる記事で役に立つように思う。
氏家先生は、マランツ#7について詳細に解説されている(あくまで感覚的にではあるが)。
先生の言う、「内部が半分ポジティブフィードバックがかかり、発振前の緊張した状態で、反応が速い」というのは、ようするに制御対象が不安定系で(例えば戦闘機のように尾翼が下にあり、俊敏な制御がしやすい)
しっかり制御がかかり、即応性がよいということなのだろうと推測する。
また、管球王国のウェスタン91Bのアンプの完全コピーの記事には、「ぷりぷりしたエナジー」とある。91Bには、20dB以上のネガティブフィードバックがかかっているが、要するに立ち上がりが速くないと、ぷりぷりしたようにはなりえない。
というわけで、ネガティブフィードバックについては、以下の記事を読んでおくべきだと思う。
①「マランツ#7型プリアンプの製作(1)~(3)」(「ラジオ技術」1998年/11月、12月、翌年1月)氏家高明
・マランツ7の精神性を理解したうえで、肝となるフォノイコライザ部分の完全コピーの方法が説明されている。お勧め!
・フォノアンプのイコライザや、cd用のプリアンプに使える。
・なお、回路定数の1つについては、後の記事で訂正されている。
②「高帰還300Bシングルアンプの製作(1)~(3)」(「ラジオ技術」1999年/4月、5月、6月)氏家高明
・本家、本来の3段の91Bアンプについて解説されている。
③「管球アンプキットを組む愉しみ W.S.I91type」(管球王国vol22 2001年秋)
・巷の2段増幅ではなくて、本家、本来の3段の91Bアンプを完全にコピーするべく挑むもので、ウェスタンの流儀について解説がある。配線の仕方も、忠実にコピー。
③-2「WE-91Bパワー・アンプの製作」(「ラジオ技術」2001年7月)新 忠篤
・本家、本来の3段の91Bアンプ、多大なブリーダ電流を流す点も、回路図上の忠実なコピー。
・配線の仕方は、コピーされていない。
④「D-NFB(NFB for Distortion only)の実験-6GB8(S)で1/400の低減率を達成!!」(「ラジオ技術」2000年/7月p44)野呂伸一
・ポジティブフィードバックを使って、ひずみを劇的に減少する。
・ただ単にひずみ低減というのではなくて、「透明感とハイスピード感」という記事内容に着目したい。
⑤「40KG6ASEPP OTLによるD-NFB実用アンプの製作」(「ラジオ技術」2001年/10月p42)野呂伸一
・上記④の応用記事。
⑥その他、無線と実験の松並先生の記事で、
「ネガティブフィードバックの量を変えると、目を見張るような変化がある」。
ラジオ技術の新先生の記事で「ボジティブフィードバックを入れると活き活きする」というのがあったが、いつの号だったかは忘れた。